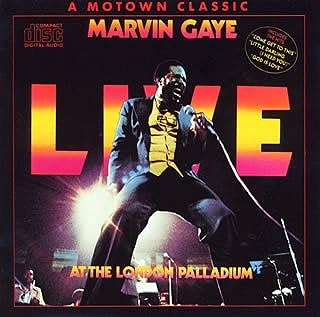97年リリース作品。ここからはっきりとドラムンベースの影響が音に出ています。ある意味音の質感は80年代に戻ったかのようです。
実はEMIイヤーズというのは大人のポップス路線で行ったのは前半だけで、途中からは電子音楽への復活劇が描かれている。というよりも、日本のポップスとして汎用性の高い音楽を目指したアプローチは高橋幸宏のソロ活動としては初期から一貫していて、ただ単に音の装飾が時代に合わせて変わってきただけだ、と考えることもできそうです。
従って、時代の要請で電子音楽が求められればそのように対応するし、そうでなければ生音中心の音楽になる。高橋幸宏の音楽はすこぶる相対的なものなんだといえるのではないでしょうか。
時代の空気がはっきりと変わった21世紀以降はYMOの再解釈に自らの活動を埋めていくことになるので、90年代はその前哨戦と捉えることもできます。ただし、その変化の兆しや確立したポップスとしての王道路線は体幹のように音楽の中心を構成することに一役買っている。そんな風に感じました。
加えてEMIイヤーズがビートニクスの2ndと3rdの間に挟まれているというのも重要な論点ですが、それはまた来月考えることにしたいと思います。